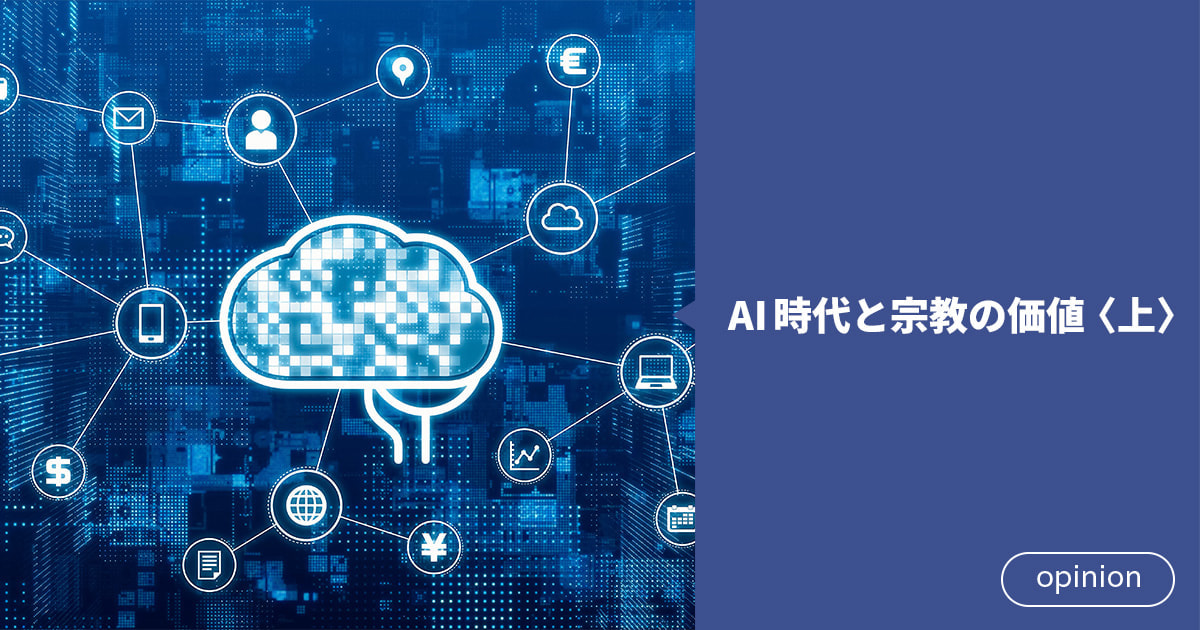AI研究の最前線からみた世界宗教・創価学会が"池田大作先生AI"をつくらない正しさ
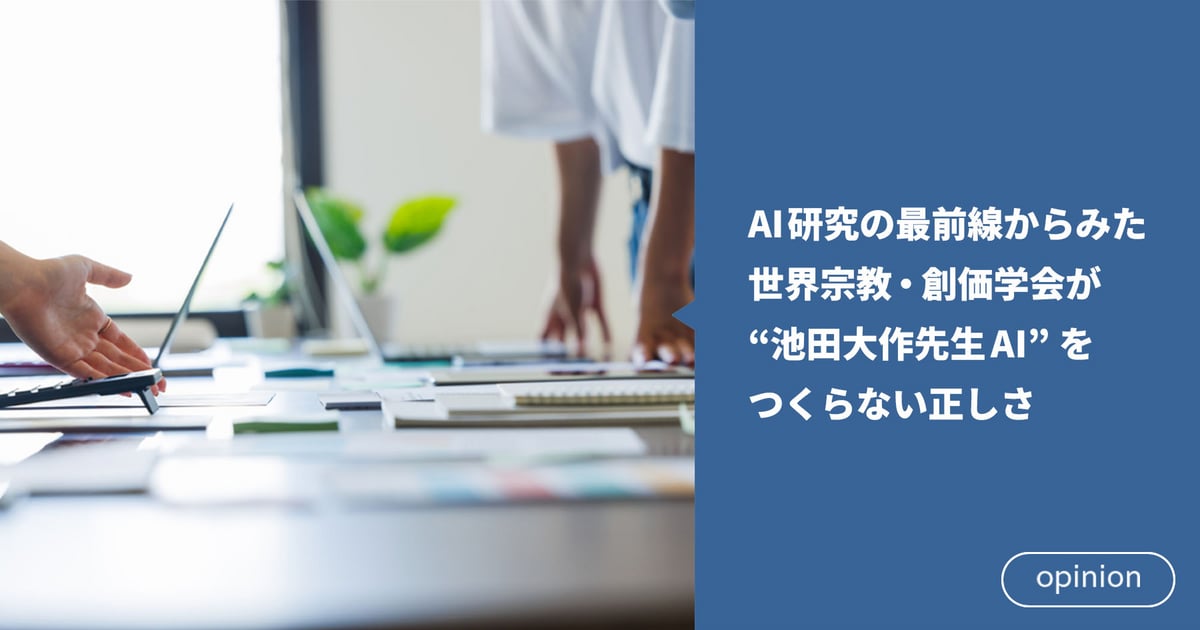
先日、ひょんなご縁から、日本におけるAI研究の第一人者にお話を伺う機会に恵まれました。
創価学会では「池田先生のご著作・ご指導を、言語生成AIを用いて検索できるサービス」の開発が推進されており、それは池田先生を模したAI、いわば"池田大作先生AI"ではなく、「先生のご著作・ご指導を、引用というかたちで提示するという、いわば"使い勝手のよい検索サービス"といった性格」であることも示されています。
なかなか得がたいチャンスでしたので、こうした学会の方向性をめぐってもご意見を伺ってみました。ご都合によりお名前は伏せさせていただきますが、差し障りない範囲でご紹介しながら、専門家の見地も踏まえつつ、世界宗教・創価学会における"池田大作先生AI"とは何か、考えてみたいと思います。
"池田大作先生AI"に「同苦」はできない
ところで、創価学会における「励まし」の根幹にあるものとは、いったい何なのでしょうか。
私なりに悩みながらたどり着いている現在地として、それは「同苦」ではないかと思っています。
「一切の人々の苦悩を、わが苦悩と受け止め、同苦していくのが仏です。真の『同苦』は、『抜苦』であり『与楽』です。たんに、哀れみを向けるだけのものではない。一緒になって悩み、具体的に、その苦悩を取り除き(抜苦)、真の安らぎと幸福を与える(与楽)まで戦うのが仏です」(「法華経 方便品・自我偈講義」)
仏とは同苦する人、だとするならば、私たち学会員もまた、「同苦できる自分」に成長していくこと、境涯革命していくことが、すなわち「人間革命」の具体的な目標といえるでしょうか。
友人を折伏していて、理屈抜きに自分の心が相手に伝わる瞬間というのが、あると思います。
そこには祈りが大切だったり、勇気が大切だったり、いろいろとありますが、そもそも「苦しみ」というものが何かを感じることができなければ、話になりません。「苦しみ」という感覚そのものが存在しない人には、「同苦」もまた存在すらしないのは当たり前です。
そこで、AI専門家の方に伺ってみました。
「AIに『苦しみ』は感じられるのか?」──答えは「かなり難しい」でした。
いわく、人間であれば、口調や表情などの身体情報から、苦しみを察することができます。しかし、今のところAIは、そういう能力がかなり低い。今のAIは「言葉」によって成り立ち、「言葉」に頼りすぎているからです。言葉、なかんずくテキストから苦しみを読み取ることの困難さが、そこにはあります。
しかも、他者の苦しみを感じる、というのは、人間の場合でも、すごく難しいことです。平気な顔をしているけれども、実は、すごく落ち込んでいる場合もあります。逆に、しんどそうだけれども、実は、単なる寝不足だったりもします。その人その人で、個人的なバイアスもあります。人間の悩みというものは奥深いもので、人間でも読み取るのが難しいものなので、残念ながら現時点のAIでは、かなり難しい、という結論でした。
また、「苦しみ」は「痛み」とも言い換えられると思いますが、身体というものをもたないAIには「痛み」がなく、AIに対して、どのように「痛み」を教えればよいのかも分かってはいないそうです。それはつまり、「人間に痛みを与えてはならない」ということの意味もAIには分からない、ということになります。
「一切衆生の異の苦を受くるは悉く是れ日蓮一人の苦」との大慈大悲が、三代会長を貫く「指導」の源泉だと思います。
「同苦」なき"池田大作先生AI"は、せいぜい"池田大作先生風のAI"にすぎないということでしょう。
"池田大作先生AI"に「人格」はない
最近、ChatGPTの5.1がリリースされましたが、好評をもって受け入れられているようです。
以前、4oから5にバージョンアップした際に起きた世界的な炎上騒ぎをご存じの方も多いと思います。騒ぎとなった最大の理由は、ChatGPTに「"人間らしさ"が薄くなった」というものでした。AIをつかまえて"人間らしさ"を云々するのが、どだいおかしな話なのですが、それほど人々が、言語生成AIに対して親近感や信頼感を抱くようになっている証左なのでしょう。
この炎上騒ぎに開発元のOpenAIは、「偉大なAIとは賢いだけでなく、話していて楽しいものであるべき」とし、新モデルをつくりました。それが今回のGPT-5.1です。
それでは果たして、AIに"人格"はあるのでしょうか、ないのでしょうか。
専門家の答えは、"意識"も"感情"ももたないAIに"人格"というものは存在せず、あるとすれば、それはユーザー側が勝手に構築している「幻想」である、ということでした。
AIは、まるで"人格"があるかのように答えを返してきます。しかし、それは「模倣」にすぎず、言語生成AIの内側で実際に何が行われているのかというと、言語生成AIは、例えば一つの返答をするのに、たくさんの返答候補をつくります。100個ぐらいつくり、その良しあしに点数(=評価値)をつけ、その点数の高いほうから、不規則に、返答として出しているそうです。
したがって、答えには常に"揺らぎ"がつきまといますし、評価値の作り方で"人格"も変わるといいます。
そうした例の一つが、冒頭にご紹介したChatGPTの"人間らしさ"騒動です。
"人格"を感じるとしたら、それは受け手側が勝手に描く幻想──つまり、"人格"を感じさせてしまった時点で、すでに何らかの幻想を抱かせてしまっているということです。そこに、なんともいえない危うさを感じます。
"池田大作先生AI"に「一貫性」はない
その危うさの根源について、専門家の方は、このような解説をしてくださいました。
現在のAIは人間の脳における神経細胞(ニューロン)の働きを模したもので、「ニューラルネットワーク」と呼ばれます。
このニューラルネットというのは、とても優秀ではあるものの、実にくせ者で、「つくる側の思い通りにはならない」という難点があります。
その中身は、専門家にとってもブラックボックスで、出てくる結果の原因が、学習させたデータによるものなのか、はたまた計算の手順やルールによるものなのか、あるいは先ほどあった評価値によるものなのか、まったく分からないそうです。そのため、どうしても不定性や曖昧性がつきまといます。
具体的にいうと、同じ質問をしたからといって、同じ答えが返ってくるとは限りません。「一貫性」というものを持たせるのが、非常に難しいそうで、現時点では、一貫性を保てるのは、せいぜい1日程度。同じ質問に対して毎日コロコロと答えが変わってしまいます。
今日言っていたことが、翌日にはコロッと変わる。先ほどのChatGPTのように、バージョンが変わってもコロッと変わる。さらに、ユーザーが100人いたら、100人が100人、異なる"人格"を想定してしまう。これでは、むしろ不信感を招く可能性のほうが高いのでは? また、言葉を覚えさせたからといって、その人の人格になるわけではなく、逆に、「似ているけれども違う」ものができて、そのほうが問題かもしれない、とも指摘されていました。
そうした文脈において、創価学会が"池田大作先生AI"という方向性ではなく、「引用」という方向性をとったことを、「正解」と明確に評価してくださっていたのが大変印象的でした。
"池田大作先生AI"は創価学会の世界宗教化に逆行
「ランダムアクセス」という言葉をご存じでしょうか。
私は音楽鑑賞が趣味で、いっときはオーディオにもはまったのですが、カセットテープでは、目的の曲を聴くためには、その前の曲から順に聞くなり早送りする必要があります。このように、端から順番にアクセスする方式を、情報処理の世界では「シーケンシャルアクセス」といいます。
一方、レコードでは、目安の溝に針を直接配置すれば、目的の曲を聴くことができます。このように、目的のデータがある場所さえ分かっていれば、それに直接アクセスできるというような方式を「ランダムアクセス」と呼びます。
本であれば、最初のページから順番に読むのが「シーケンシャルアクセス」、目次を見て該当のページまで一気にめくるのが「ランダムアクセス」ともいえるでしょうか。
作家の佐藤優氏は、「世界宗教の条件」として、「正典化」と「ランダムアクセス」を挙げていました。
「正典」というのは、その宗教が信仰と行動の規範とする基本文書のことです。そして、正典は"閉じている"──つまり完結していることが重要となります。
創価学会でいえば、御書と小説『人間革命』『新・人間革命』が、正典の筆頭に挙がるでしょう。
そして、こうした正典に対して、先ほど述べたように「ランダムアクセス」が可能であることによって、正典の中から、今、目の前で起きていることに即した指針を、誰もが選び出すことができます。すなわち、正典を未来にわたって「応用」し続けていくことが可能になるわけです。
このように考えると、「池田先生のご著作・ご指導を、言語生成AIを用いて検索できるサービス」は、「正典化」×「ランダムアクセス」を大幅に拡大・拡充する画期的なソリューションともいえるのではないでしょうか。
かたや、"池田先生の新しい指導"を生み出し続け、正典を閉じようとしない"池田大作先生AI"は、創価学会の世界宗教化を阻害し、逆行させるものでしかなく、しかも、一貫性なく生み出し続けてしまう点で弊害しかないと、私は思います。
「後継の真髄」
池田先生が本部幹部会をご欠席され、「私を頼るのではなく、君たちが全責任をもって、やる時代である。私は、これからも君たちを見守っているから、安心して、総力を挙げて広宣流布を推進しなさい」と一切を弟子に託された2010年6月、この時のメッセージで先生は、こうも綴っておられました。
「法華経の会座において、幾度も繰り返される弟子の誓願があります。それは、"私たち弟子は、師匠の仰せ通りに広宣流布を成し遂げます。どうか、ご安心ください。心配なさらないでください"という誓願であります。弟子たちが、本気になり、一丸となって、不惜身命の祈りと行動を起こしてこそ、真実の勝利がある。これが、法華経の後継の真髄なのであります。ゆえに、私は、きょうは、あえて出席いたしません」
もし、"池田大作先生AI"が許されるのだとしたら、この池田先生の2010年6月から2025年11月までの時間というのは、いったい何だったというのでしょうか。
池田先生の三回忌、そして創立95周年の2025年11月から、次なる目標は、先生の七回忌となる2029年11月15日、そして、創立100周年の2030年11月18日──私は"あの日"の誓願のままに、胸中の池田先生と対話しながら、「後継」の道を歩んでいきたいと思います。