バズらないけど「中道」の安心感 怒りの海のイカリ
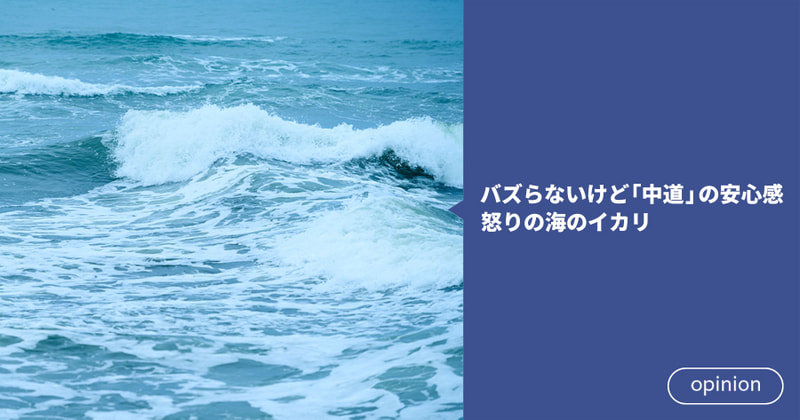
XやYouTubeを開けば、政治家や支持者を名乗る人たちの過激なメッセージが目に入ってくる。
「このままじゃ日本は終わる」とか「真実は隠されている!」とか。
SNSは一面、煽りや極端な言説があふれる「怒りの海」です。
強い言葉ほど、人の興味をひくし、心に残りやすい。インプレッション(表示数)を稼ぐ意味から、SNSでは強い言葉や表現が好まれるのは知っているんですが、こういうのを見るたびに「世の中そんなに単純じゃないよね~」と思っている人は私だけじゃないでしょう。
正義と悪、味方と敵――そんなわかりやすい図式の中に、私たち全員が当てはめられるはずもないわけで。
事実よりも感情への訴求
令和の世に立ち上がった政党が、こうした極端な言説を拡散して支持を伸ばしています。
彼らはSNSや街頭演説のライブ配信を通じて、若い世代にも浸透している。それまでの政治を否定し、社会の不満を特定の対象が原因であるとみなし、強い言葉で批判する。
それが「既存のメディアに頼らない」「自分で選んだ」という実感を与えられるからでしょう。ただ、過激なメッセージは、ともすれば事実の積み上げよりも「感情への訴求」を重視することになりかねず、傾倒への危うさを感じます。
外国人の排斥、ジェンダー平等への反対、政府や与党、官僚に対する批判……。
SNSにおいて、排他的な主張が多くの「いいね」を獲得しています。SNSだけの話ではありません。選挙で掲げる公約や政策にもこうした排他性が見え隠れし、政治家は平然とその必要性を人々に語っています。
そして、こうした主張を掲げる政党が、地方議会でも国政選挙でも、ひたひたと議席を獲得し、現実の政治に影響力を持ち始めている。政党や政治団体が、一部の属性の人の優位性を示したり、利益を強く主張したりする一方で、それ以外の人たちや、自分たちの意に沿わない人たちに対し、邪魔な存在かのように扱う言説が飛び交うのを見るたび、これが当たり前になってはいけないという危機感を覚えます。
すべての人の幸福
政治の目的は、言うまでもなくすべての人の幸福の実現です。
「選挙によって選ばれた代表者は、国民や住民の代表者となります。したがって、その代表者が職務を行うに当たっては、一部の代表としてではなく、すべての国民や住民のために政治を行うことになります」(総務省ホームページ)
を引くまでもなく、政治家は「支持者のための政治」をする存在ではありません。
「一方は救われるべき存在、もう一方は救われなくてよい存在」という線引きを、権力の側である政治が行うことは許されません。
もし「一部の属性の人たちは、政治の恩恵を受けなくてもよい」と考える人たちが力を持つようになれば、民意を理由に公的な差別や社会通念が生まれかねないからです。
現実は複雑で、何かの問題を解決しようとすれば、”あっちを押せばこっちが引く”ようなトレードオフの関係に悩むことになりますし、絡まった糸をほぐすような難しさを伴います。
さまざまな立場・意見の代表者が集まる政治という場において、自らと対極にいる存在をカットすれば万事解決する、というやり方は、まず通用しません。
だからこそ、多くの人の意見をまとめあげる存在、もっといえば「極端な方向にふれない」中道の姿勢を貫く政党が重要になると思います。
中道とは「極端に走らない、中正の道。一方に片寄らない穏当な行き方」(日本国語大辞典)と定義されますが、本来は「道に中(あた)る」という意義があり、正義や道理に適うものともいわれています。
同志社大学の吉田徹教授によれば「日本の有権者の約8割が持つ政治意識は中道で、右でも左でもないという人が大多数に上る」そうです。ネットでは極端な意見が目立ちますが、有権者の大多数は「ほどほど」がいいと思っている人たちなのです。
イカリのような存在
創価学会が支援する公明党は、そうした「中道」の立場を一貫して掲げている政党です。
わかりやすい「敵」をつくって憎悪や分断を煽るのではなく、異なる立場にいる人たちと粘り強く話し合い、合意を積み重ねていくことを大切にしています。
これは、早計に結論を出したり、すぐに相手を批判して叩くようなやり方の対極にある、最も大変な道です。
なぜ、公明党がそのようなスタンスを貫いているのでしょうか。
私は、創価学会の「すべての人が尊い」「誰もが幸福になれる」という日蓮仏法の人間観が、公明党の底流に流れているからだと思います。
年代も社会での立場もばらばらで、個人の考え方も幅広い人たちで構成される創価学会では、こうした人間観を共有したうえで、会員・非会員を問わず、お互いを理解するための「対話」が日常的に行われています。
評論家の與那覇潤氏は、
「創価学会には座談会など、相互の対話を重んじる文化があり、公明党のスタンスにも反映されています。極端な主張をぶち上げ、有権者をあおって操ればよいとする風潮にストップをかける、中道の精神の基盤になるものです」(「創価新報」24年10月号)
と述べていました。
公明党がこうした”対話の文化”の土壌を基盤にしているからこそ、極端な主張に振り回されない、安定した政治の実現に寄与することができるし、相反する片方を切り捨てるような主張にならないのだと納得しています。
……正直なところ「中道」とか「対話」とか、めちゃくちゃ地味です。
SNSのタイムラインでバズるような、ド派手なフレーズや煽り系の発信のほうが、はるかに目立てるに違いない。
でも「目立つこと」と「信頼されること」はぜんぜん違う。
公明党には“目立たないけど信頼できる”、他党の追随を許さない実績の積み重ねがあります。
公明党には、一時の流行や大きな声に振り回されず、分断や対立が深まる時代にあっても、社会を安定の方向へとリードする役割であってほしい。
そう信じられるからこそ、この時代に公明党がいてくれることに、私は安心を覚えるのです。
東京大学大学院教授の堺家史郎教授が「中道政党が存在感を増すことは、基本的には良いことだとされています。左右両極のポピュリズムに対する、ある種の防波堤のような存在になるからです」と述べたように、極端な意見がじわりと支持の度を増す傾向にある日本では、イカリのような役割を果たす存在は、いっそう重要になるに違いありません。



