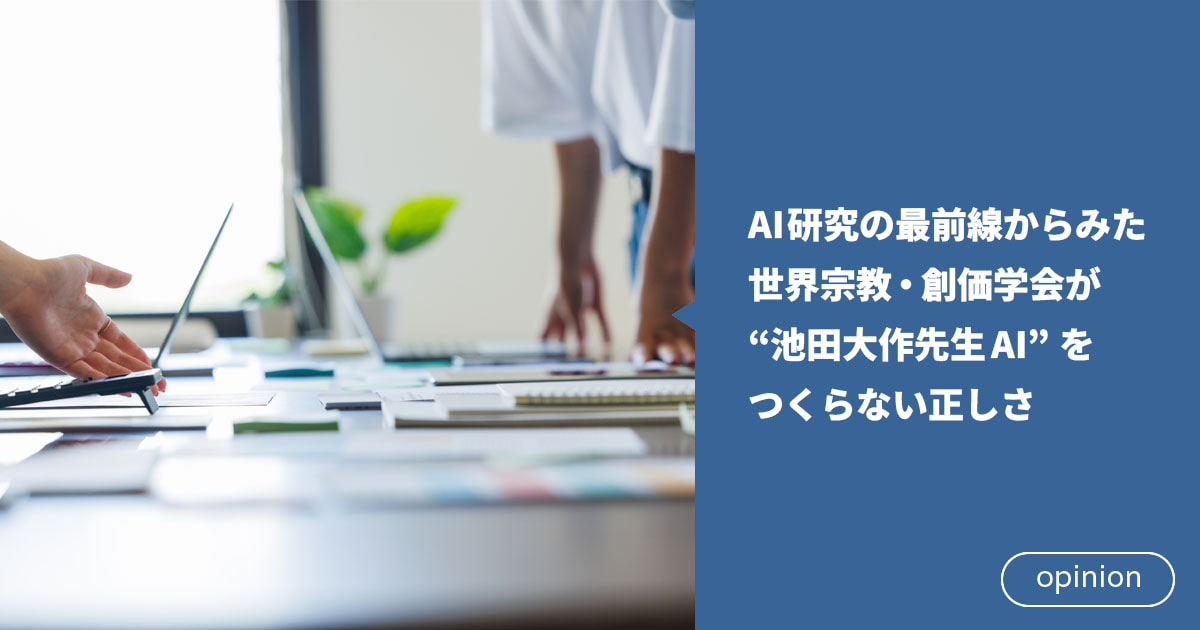創価学会が"池田大作先生AI"をつくらないワケ

池田大作先生の三回忌となる2025年11月15日──「11・15」が間近に迫ってきました。
あの日を境に読み返し始めた小説『人間革命』も、現在、第12巻。池田先生が遺してくださった言々句々と向き合い、胸中の池田先生と対話しながらの悪戦苦闘は、池田門下生の一人として「I am Shinichi Yamamoto」への"発迹顕本"の日々だったといえるのかもしれません。
ところで、2025年1月に開催された第6回本部幹部会の席上、原田会長から「池田先生のご著作・ご指導を、言語生成AIを用いて検索できるサービス」の開発推進が発表されました。
そこでは、そのサービスが、池田先生を模したAI、いわば"池田大作先生AI"ではなく、「先生のご著作・ご指導を、引用というかたちで提示するという、いわば"使い勝手のよい検索サービス"といった性格」であることも示されています。
なぜ、"池田大作先生AI"ではないのかについては、
1.言語生成AIには、本当の意味での指導や激励などは、本質的に成し得ない
2.AIの回答を「正解」と捉えて事足れりとする姿勢は、信仰の在り方として適切ではない
──という2点が、挙げられていました。
ここでは、創価学会が"池田大作先生AI"をつくらない理由について、それでも一面的にはなると思いますが、私なりに深掘りしてみたいと思います。
AIの限界
まず大前提として、どのようなAIサービスであったとしても、大元では、ChatGPTなどに代表される大規模言語モデル(LLM)が稼働し、サービス全体を支えています。
もし、"池田大作先生AI"が存在しているとしたら、あなたは、どのようなことを聞いてみたいと思いますか?
おそらく、初めて直面するシチュエーションに対して、「池田先生なら、どう考えるだろうか」「池田先生なら、どのように判断されるだろうか」──そのような思いから、質問されることも多いのではないでしょうか。
しかしながら、こうした期待とは裏腹に、LLMには、そもそもの限界が存在しています。
もし"池田先生AI"をつくったら
その限界とは何か。
第1に、LLMは、学習したことからしか正確な回答を生成できません。学習データにはない未知の情報や、まったく新しい事象に対する予測や生成はできないのです。例えば「LGBTQ+」などについて質問しても、"池田大作先生AI"には、そのものズバリで答えることはできません。
では、そうした場合、"池田大作先生AI"は、どのような振る舞いをするのでしょうか。
ここに、LLMは事実とは異なる情報を生成することがある、という第2の問題が発生します。
LLMは、学習していないことでも無理くり回答を返そうとします。素直に「分かりません」とは言わず、"もっともらしいウソ"をつくのです。そのため、特に未知の情報や、まったく新しい事象に対する予測や生成といった不確実な領域では、非常に注意が必要です。 "池田大作先生AI"がウソをついた時、それをウソと冷静に見極められる人が、どれほどいるでしょうか。
第3に、LLMの学習データには少なからず偏りが存在しており、生成される回答にも、その偏りが反映されてしまいます。ChatGPTにおいても、ジェンダー、人種、政治的イデオロギー等々の面で、バイアスの存在が指摘されています。"池田大作先生AI"が、突如として差別的な主張や、著しく保守的あるいは革新的な主張などを語り出す可能性があるのです。もしも、そのようなことが万が一にも起こってしまったとしたら、池田先生への世界的・社会的な信頼は失墜してしまうでしょう。
最後に第4、人間には元来、「AIが人間のような感情を持っている」と錯覚してAIに対して感情移入してしまう傾向があり、過度に信頼・依存してしまう危険性があります。
こうした現象を「イライザ効果」と呼びますが、しかしながら、LLMは人間のような、価値観、感情、直感、などは持ち合わせず、現在主流となっているLLMは「文脈に基づいて、次に来る単語を確率的に予測する」という動作を繰り返すことで、回答を生成しているにすぎません(それ自体、大変に素晴らしいことであるのは、いうまでもありません)。したがって、複雑な倫理的判断を伴う回答はできません。
「価値観」も「感情」もないところから生み出された言葉が、"池田大作先生の言葉"となってしまう──とすると、「言と云うは、心の思いを響かして声を顕すを云うなり」という日蓮大聖人・創価学会の"言葉観"への全否定に通じてしまうと考えます。
以上をまとめると、初めて直面する出来事や不確実な未来に対して、「池田先生なら、どう考えるだろうか」「池田先生なら、どのように判断されるだろうか」という問いに答えを出すことは、その成り立ちからしてAIには難しい、という結論にたどり着いてしまうのです。
池田大作先生の師弟観
池田先生は、このようにご指導くださっています。
「大きな理想というものは、師と弟子とがそれを共有し、弟子が師の遺志を継いでこそ、初めて成就していけるものである」 (『広宣流布と世界平和 池田大作先生の指導選集 下』)
弟子において大事なことは、師の「志」を受け継いでいるか否かにある、ともいえるでしょうか。
そして、先生は続けて、こうも語られています。
「師匠と弟子とは、針と糸の関係にもたとえられよう。師が道を開き、原理を示し、後に残った弟子たちが、その原理を応用、展開し、実現化していく」(同)
師が示した原理を「応用、展開し、実現化していく」には、師の志を受け継いだ弟子の「自立」が欠かせない──それを先生は、「針と糸の関係」にたとえられたのだと思います。
さらに先生は、付言されています。
「また、弟子は師匠を凌いでいかなくてはならない」 (同)
ここに立ち至って、「池田先生なら、どう考えるだろうか」「池田先生なら、どのように判断されるだろうか」という問いすらも、先生が教えてくださっている「弟子の在り方」からすれば未熟なものにさえ見えてきてしまいます。
このように考えてみたとき、"池田大作先生AI"の必要性などは、そもそも存在せず、もし仮に、その選択を求めるとするならば、それは“弟子の甘え”がなせるものといえるのではないでしょうか。
WhatではなくWhy
現在の技術をもってすれば、"池田先生がおっしゃりそうなこと"を、"池田先生のような言葉遣い"でAIに生成させることはできますし、さらには"池田先生のような声や口調"で、"池田先生のような映像"に、語らせることも可能です。
しかしそれは、どこまでいっても"池田大作先生のようなAI"であって、"池田大作先生"ではありません。
それどころか、先述したように、差別的な主張をしたり、もっともらしいウソをつく可能性のある存在が、"池田先生の仮面"をまとうことの危険性は計り知れません。
編集工学研究所で代表取締役社長を務める安藤昭子さんが、聖教新聞のインタビュー(2025年3月2日付)で語っていた内容は、大変、示唆に富んでいました。
「創価学会には、多くの言葉が残されていると思いますが、そうした言葉からも、師の息づかいを感じることができますね。編集工学研究所では今、『探究型読書』というものを発信しているのですが、これは、松岡(=同研究所を設立した松岡正剛氏)の読書の仕方を『方法』として学び、多くの人が活用できる型にしたものです。ぜひ書籍や言葉から、"師匠が何を考えていたのか" "なぜそう考えたのか"を学ぶお役に立てれば幸いです」
弟子が師の息づかいから感じ取るべきは、"What "ではなく、「なぜ、そう考えたのか」という"Why "なのではないでしょうか。
小説『新・人間革命』の「はじめに」に池田先生は、その執筆は「限りある命の時間との、壮絶な闘争となる」と記されました。
「限りある命の時間との、壮絶な闘争」 ──そこに"池田大作先生AI"がつけ込む余地は、ないのだと思います。
"出でよ、幾万、幾十万の山本伸一よ!"
この池田先生の叫びに、祈りに、呼応する自分自身でありたいと、「11・15」を前に決意を新たにしています。